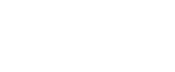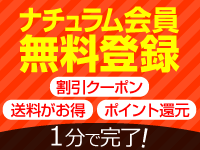2018年04月13日
慰められたのは事実だっ
自宅最寄り駅より二つ手前で降り、伊良部総合病院へと向かった。何時問も前から、そうすることは決めていた。自分をわかってくれるのは伊良部しかいないと思った。
「やあ、大森さん。久しぶり」
伊良部はいつもと変わらぬのんびりした口調で迎えいれてくれた。三日会わなかっただけなのに、三年ぶりのような気がした。うれしくて抱きつきたくなった。情けないことに目に涙が滲んだ。
「どうしたの。花粉症?」
おい、もう夏だろうが。でも彼の存在自体がありがたかった。
「先生、実はね……」
和雄はこの三日間、会社に缶詰だったこと、その間泳ぐことができなかったこと、部下に佐藤という馬鹿がいてエライ目に遭ったことなどをいっきにまくしたてた。口が勝手に動いていた。言葉がいくらでも溢れでてきた。
体調が最悪であることも訴えた。内臓が学級崩壊だとおなかを抱えこみ、おくびを吐いてみせた。
「大丈夫だよ。すぐに治るから」伊良部は何事でもないように言った。
「そうなんですか」本当に抱きつこうかと思った。
「うん。だってそれって典型的な禁断症状だもん」
「禁断症状?」
「そう。泳がなかったことが原因。ぼくも大森さんも、もう泳がないと体調が維持できない身体になってるんだよね。だから今夜泳げば元に戻るよ」
「……それって、まずくないんですか」
「全然」平然と言い放っている。
「いや、でも、全然ってことは……」
「アルコール依存症じゃないだけラッキーだと思わなきゃ。酒だと内臓がやられちゃうでしょ。でも水泳だと身体が引き締まるし、血行もよくなるし、とくに不都合はないじゃない」
「はあ……」
「会社依存症とかボランティア依存症だとか無農薬野菜依存症とか、人間にはいろいろな依存症があるけど、水泳なんてのはもっとも害がないんじゃないかな」
「いや、その、できるなら、どんなものでも依存症は避けたいんですが……」
「大丈夫だって。そのうち飽きるよ」呑気に笑っていた。「心身症なんてのは神の采配なんだから、自分じゃ抗《あらが》わないこと。『なすがままに』がいちばんなんだから」
「飽きます、かね」
「飽きる、飽きる。あっはっは」
納得はできないが、慰められたのは事実だった。伊良部はいい精神科医なのかもしれない。そんなことを思いはじめた。少なくとも、自分の心を落ちつかせてくれるのだから。
「ところでさあ」伊良部が声をひそめて言った。「今夜あたり、プールに忍びこもうと思ってるんだけど、大森さんもどう? 午前零時、区民体育館前」
「ほんとにやるんですか」
「うん。やっぱり五時間ぐらい続けて泳いでみたいじゃない」

「いや、でも、ぼくは……」
和雄が答えに詰まる。
「そう言うと思った。大森さん、けっこう常識的だもんね」
なんだか気の小ささをからかわれているような気がした。
「だったらぼく一人でやるけどさ」
たいした度胸だ。
「ただ、大森さんにひとつだけ協力してほしいことがあってさ」伊良部が身を乗りだす。和雄も背中を曲げ、耳を傾けた。「あの区民体育館って裏にトイレの窓があるわけ。最初はその窓を割って入ればいいだろうと思ってたんだけど、できることなら器物破損は避けたいじゃない」
「ええ」
「今夜、大森さんはプールに行くわけでしょ。そのとき、トイレの窓の鍵をドライバーを使って外しておいてくれないかなあ」
「トイレの窓の鍵を、ですか」